《 山形県醤油味噌工業協同組合へのご連絡はこちら 》
Q&A
醤油 Q&A
醤油の歴史について
醤油の原形は、いまから3000年以上も前の中国の「醤」に始まります。 これはもともと原料を塩漬けにして保存したことから始まり、紀元前700年頃に中国の法律の中に 「醤(ひしお)」の文字が見られます。これがいつ日本に伝わったかは定かではありませんが、 西暦500年代の前半に中国から伝わったと言われています。
中国から伝わったといわれる「醤(ひしお)」は、使用した原料により分けられます。 果実、野菜、海草などを材料にした「草醤(くさびしお)」、魚や肉を使った「魚醤(うおびしお)、 肉醤(ししびしお)」穀物を原料とする「穀醤(こくびしお)」などがあり、その中でも米・小麦・ 大豆を使用した穀醤(こくびしお)が醤油の原型と考えられています。
当時の中心的な醤(ひしお)は、魚介類を主要な原料とした「魚醤(うおびしお)、肉醤(ししびしお)」 と考えられていますが、その中で「穀醤(こくびしお)」が日本で発達したのは菜食が主体となった日本人の食生活によく合うことや、 他の醤よりも保存性がよかったことなどによるものといわれています。
醤油のルーツをたどると「醤(ひしお)」にたどり着きます。小魚、鴨、鹿、野菜、果物、穀物などが使われたようですが、 その中で魚を原料に使ったものを魚醤といいます。日本での魚醤の歴史は古く弥生時代から古墳時代には塩漬け発酵食品が作られていました。
これが現在の魚醤の原型といわれています。その後、醤油が使われるようになってからは、 魚醤はごく一部の地域で伝統的に利用されている程度になっていました。最近、天然志向やエスニック料理の普及によって、 魚醤の独特の味が見直され、新聞や雑誌などでも注目されるようになってきました。ちなみに日本の3大魚醤は、秋田の「しょっつる」、 奥能登「いしる、いしり」、香川の「いかなご醤油」。東南アジアでは、タイの「ナン・プラー」、ベトナムの「ニョク・マム」が有名です。
日本の醤油の国際化の始まりは、江戸時代。江戸時代の日本は、鎖国の時代でしたが、 唯一の例外として長崎でオランダと中国との貿易が許されていました、日本の醤油がオランダ船と中国船によって中国本土、 東南アジアやオランダ本国まで運ばれたのが始まりです。
醤油の原料と製造法について
醤油の主な原料はうまみのもとになる「大豆」、香りや甘味のもとになる「小麦」、そして「食塩」です。 これらの原料は国内産のものも使用されますが、現在はほどんと輸入に頼っています。ちなみに大豆は約98%が、 小麦は約82%、食塩86%が輸入。主な輸入先は大豆はアメリカ・中国、小麦はアメリカ・カナダ、食塩はメキシコ・オーストラリアです。
「脱脂加工大豆」とは、醤油の原料用として大豆から、あらかじめ油をとりのぞいたもの。 一方、大豆そのままのものを「丸大豆」と呼びます。昔は、醤油の主原料の大豆は丸のままの大豆(以下丸大豆と呼ぶ)が使用されましたが、 丸大豆には多量の油脂が含まれており、これが、醤油のもろみをしぼった生揚醤油の上に醤油油(あぶら)として浮んできたために、 取り除いていました。そこで、丸大豆の油をあらかじめ取り除き、醤油の原料用として加工された大豆すなわち「脱脂加工大豆」 と呼ばれるものを使うことが主流となったのです。このとき取り出した大豆油は、食用油として有効活用することができるようになりました。 味や香りは各人のこのみですが、一般的には、脱脂加工大豆で作られた醤油は「香りの立つキレのある風味」、「強いうま味」を特徴とし、 丸大豆で作られた醤油は大豆の油脂成分が醸造中にグリセリンなどに分解され「まろやかさ」、「深いうま味」が特徴の醤油となります。
遺伝子組み換え大豆とは、除草剤によって枯れないようにするために特別な酵素をつくる遺伝子を大豆の中に入れたもので、 有害ではないということが厚生労働省から発表されています。現在、醤油に使用されている原料大豆(または脱脂加工大豆)には、 遺伝子組み換えでない大豆(または脱脂加工大豆)と不分別の大豆(または脱脂加工大豆)とがあります。 醤油は醸造期間が6~8カ月かかり、その間に、大豆たんぱく質が分解されて製品からは検出されないため、 遺伝子組み換え大豆を使用した場合でも表示は義務づけられていません。 しかし、消費者の間に遺伝子組み換え食品について表示を求める声が高いので、遺伝子組み換えでない大豆を使用して製造、 販売をする際の原材料表示のガイドラインを自主的に決めて、表示するようにしています。
※遺伝子組み換えについては「ここをチェック! 表示と保存法」でもご紹介しています。
醤油のつくり方はJAS(日本農林規格)によって醸造方式が3つに区分されています。それは「本醸造方式」 「混合醸造方式」「混合方式」の3つです。醤油のつくり方では「本醸造方式」がもっとも一般的ですが、 「混合醸造方式」と「混合方式」の2つは原料の大豆のたんぱく質を塩酸で分解してつくったアミノ酸液などを使用します。 この方式でつくられた醤油は、独特の香りとうまみがあり、地域によってはこの風味が好まれます。 なお、アミノ酸液と同様な使い方として、酵素分解調味液や発酵分解調味液があります。
日本の醤油の国際化の始まりは、江戸時代。江戸時代の日本は、鎖国の時代でしたが、 唯一の例外として長崎でオランダと中国との貿易が許されていました、日本の醤油がオランダ船と中国船によって中国本土、 東南アジアやオランダ本国まで運ばれたのが始まりです。
醤油の製造過程には、蒸した大豆(脱脂加工大豆)と炒った小麦を砕いたものを混合し、そこに種麹を加えて、 麹をつくるという工程があります。この醤油麹に食塩水をくわえて、大きな桶やタンクに入れて仕込むことでつくられるのが 「もろみ」です。もろみは、仕込み桶やタンクの中で6カ月以上かけてねかされて発酵・熟成し、 醤油特有の香りやうまみ成分をつくっていきます。
本来、醤油は添加物を加える必要の少ないものですが、酵母の一種である白カビの発生を防ぐ目的で、 アルコールや保存料を加えることがあります。また、地方によっては甘い醤油が好まれるために甘味料が加えられたり、 色の調整のためにカラメル色素が加えられることもあります。これらの添加物を使用した場合には、 原材料の表示欄に必ず表示しなければなりません。この表示がないものは、添加物を使用していない醤油です。
スーパーなどで販売されている1リットルの醤油を作るには、大豆と小麦とをそれぞれ約200g、 塩は約160g必要です。なお、丸大豆醤油の場合は大豆が230gほどになります。
原料である大豆と小麦を、麹菌をはじめとする微生物の力のみで醗酵・熟成させて醸造した本醸造醤油のうち、 醸造を促進するための酵素や食品添加物を使用しないものにだけ「天然醸造」の表示ができます。 これは、醤油のJAS規格と品質表示基準で決められています。
醤油の醸造期間は温度によって異なりますが、現在はもろみの発酵・熟成に最適な温度にコントロールできるようになったため、 おおむね6カ月でできあがります。この間、大豆タンパク質や小麦のでんぷんが分解・発酵され、さまざまな成分が作用し合って熟成し、 醤油の色、味、香りが完成しますが、これは完成後、時間がたつと色が濃くなったり、香りが変化したりします。 そのため、醸造期間が長いほどいいとは言い切れません。
醤油の種類について
日本農林規格(JAS規格)では、「こいくち」「うすくち」「さいしこみ」「たまり」「しろ」の5種類に分類しています。
それぞれ特徴のある味わいを持ち、それらを生かしたいろいろな使われ方をしています。
こいくち
現在、日本の醤油消費量の80%を占める醤油。つけ、かけ、煮もの料理や合わせ醤油にも適しています。
うすくち
色が淡く、料理の色や味わいを生かす関西料理に欠かせない醤油です。
たまり
トロリとしたコクのある味が特徴で、「さしみだまり」と言われるように、つけ醤油に使われるほか、照り焼き、煮物、せんべいなどにも適しています。
さいしこみ
「甘露醤油」とも呼ばれ、色も味も濃厚な醤油です。つけ・かけ醤油に最適です。
しろ
うすくち醤油より、さらに色の薄い醤油です。料理のでき上がりをうすい色に仕上げたいときに使われます。
日本農林規格(JAS規格)では、醤油を「特級」「上級」「標準」の3段階にわけ、それぞれの段階ごとに色度、全窒素、無塩可溶性固形分、 アルコールなどの規格を設定しています。このうち、最も重要なものは全窒素分です。これは、醤油の旨味の素であるアミノ酸各種が全て窒素を含んでいるので、 全窒素分を計ることによってアミノ酸の量が推定できるためで、この数値の高低によって等級が決められています。ちなみに特級と特選の違いも窒素分で表し、 特級より窒素分が10%以上多い(こいくちで窒素分1.65%以上)醤油は「特選」、20%(こいくちで1.80%)以上の醤油には「超特選」の表示をしています。 ただし、この特選、超特選の表記は任意であるため、全窒素の含有率では超特選基準のものでも「超特選」の表示をしていないものもあります。
醤油の場合は「淡口」と書くのが一般的です。「薄口」と記述すると「濃口」醤油よりも「味が薄い、塩分が薄い」 醤油という誤解を与えかねないため、醤油業界では古くから「淡口」を使用しています。うすくち醤油の本来の特徴の一つである 「色が淡い(あわい)」ということから「淡」という文字を使います。
「減塩醤油」は血圧の高い人、心臓・腎臓・妊娠中毒毒症などで減塩食を必要としている人向けに開発された醤油です。 食塩分は通常の醤油の50%以下(9%)で、厚生労働省の「特別用途食品」として指定されています。一方、 「うす塩醤油」は成人病の予防を心がけている人たちに適した醤油で、食塩分は通常の醤油の80%以下(13%)。つまり、 「減塩醤油」と一般の醤油のちょうど真ん中くらいの塩分のものが「うす塩」です(あま塩醤油、あさ塩醤油という名前の醤油も同じです)。 減塩醤油は通常の醤油を製造後、塩分だけを特殊な方法で取り除き、旨味、香りなど、他の成分はそのまま残してつくります。 減塩食を必要とする人、塩分の取り過ぎが気になる人など健康志向から減塩醤油・うす塩醤油を使う人が増えています。
醤油の製造過程で雑菌が繁殖しないためには、適切な塩分が必要です。そのため減塩醤油には、 いったん通常の醤油をつくってから塩分だけを約半分減らす工程が必要になります。減塩醤油は通常の醤油よりも若干高い値段になるのは、 そのためです。
醤油には地域の嗜好や産品、調理方法の違いなどによって、微妙な違いがあります。赤みの魚の多い東日本でその臭みを消す香りの高いこいくち醤油が普及したり、 だしで素材を煮ふくめて醤油で仕上げる調理法が主流の関西地域で、うすくち醤油が誕生し普及したのも、地域に根差した醤油の違いといえます。 また古くから中国や韓国の味との接触が多い九州では、甘味の強い醤油が使われています。最近は人の交流も多く、地域差は少なくなって来ていますが、 現在でも各地で地域特性に合った醤油が作られています。
醤油のおいしさについて
通常こいくち醤油は約16%、うすくちが約18%です。
食べ物は全てpH(酸性・アルカリ性の程度の尺度)をもっていて、その数値によって人はおいしさを感じます。 pHは7が中性で、pHが0~7が酸性、7~14の場合はアルカリ性。私たちがおいしいと感じるのは、pHが酸性に寄っているときです。 醤油のpHは一般的に5前後で、最もおいしさが感じられる弱酸性になっています。 アルカリ性の納豆や生卵に醤油を加えるとおいしく感じるのは、醤油に味を酸性にもどす力があるからなのです。
醤油には、ぶとう糖を中心に約15種類もの糖分が3~5%含まれています。 また、他にもグリセリンをはじめとするさまざまな糖アルコールやグリシンのような甘味をもつアミノ酸などがあるため、ほんのりとした甘味が生まれるのです。
一般的に醤油の色は赤みがかった透明な褐色です。この色はアミノ酸と糖分を混合し、加熱したときにできます。この美しい色を称して「むらさき」の異名をもちます。
醤油の保存法について
醤油の中のアミノ酸と糖は、化学変化によってメラノイジンという物質をつくります。 このメラノイジンが、酸化により色が濃くなるという性質があることから、空気に触れると酸化現象を起こし、 醤油の色を濃くするのです。この現象は、温度が高かったり、直射日光があたるとさらに促進し、色が黒ずむと同時に風味も落ちて、 品質も劣化します。醤油は日の当たらない温度の低い場所に置くようにしましょう。
醤油の表面に浮いた白いものは、カビです。これは酵母の一種で、健康に害はないので、ペーパータオルなどで濾せば、使うことができます。 ただし、風味は落ちているので、火を通して早めに使ったほうがいいでしょう。
めん類や鍋物などに用いられるつゆ類は、食塩分が醤油とくらべて低いので、腐敗しやすいといえます。 開栓後の賞味期間は、ストレートで使うもので約3~5日、2倍濃縮のもので2~3週間、 3倍濃縮のもので1~1.5カ月です(容器がガラスびんの場合)。開栓前は直射日光を避けて涼しいところに保管すれば、 長期保存しても酸敗・腐敗しにくいです。なお、商品のラベルに賞味期限の年月日表示が記載されていますので、 それを目安にしてください。
JASの格付け(特級・上級・標準)は、平成15年6月9日までは農水省の登録格付機関である(財)日本醤油検査協会で格付の合否を認定していました。 平成15年6月10日以降はJAS法の改定に伴い、農水省の登録認定機関「(財)日本醤油検査協会」の認定を受けた新認定工場が、 自ら格付けしてJASマークを添付するようになりました。
醤油や醤油の加工品の容器には、分別収集を見分ける方法として法律にそって次のような見分けマークがついています。 表示に従って、正しい分別をし、リサイクルにご協力ください。ガラスびんはひと目でわかるので、 表示の必要はないと定められております。

容器包装リサイクル法では、PETボトルについて自治体の分別収集、消費者の分別排出の際、キャップをとり、洗って、 つぶしてから出すように決められています。しかし、取り外しの難しい中栓、リング、ラベル、取っ手などは、 自治体から引き取った業者がリサイクルの過程で処理することとなっているので、無理にはずす必要はありません。
その他
大漢和辞典(諸橋徹次先生監修)によると、「醤油」の「醤」という字は、古くは「〓」と書かれていたとのこと。 「醬」の字は、胸や腸という文字に使われている「月」に相当し、にくづき篇で肉を意味します。 また、「爿」は「ショウ」という音を表しもの。さらに、下の「酉」は「酒」と同じで、ものを蓄えて醗酵させる甕の形からきています。「醤」の古い本字「醬」は「乾肉を切り麹と塩を加え、 酒を注いで甕の中に密封してつくるので「月」(肉)と「酉」(酒)とをあわせてその意味を表したものと解説されています。 また、「醤油」の「油」という文字は、とろりとした液体を意味し、「醤」の字に合わせて使われたと考えられます。古い中国には「油油」(悠々)と言う言葉があり、 「おもむろに流れる様」という解説がされていますから、とろりとした液体という意味にもつながります。室町時代の文献の中には「醤油」という文字に「しょうゆう」 という読み方がついているものがあるので、むかしは「しょうゆう」と発音していたのかも知れません。
[醬……將(しょう)の下に酉(とり)]
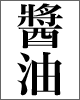
醤油を「むらさき」というようになったのには、諸説があります。
1. 昔の人は赤褐色のことを紫と言い、小皿に垂らしたお醤油の色が赤褐色だったため、以来お醤油のことを「むらさき」と呼ぶようになったという説。
2. 江戸時代は、江戸が政治の中心となったものの、文化の面ではまだまだ京や大坂に遅れをとっていた時代。江戸に独自の文化を隆盛させようとしていた支配階級の武士たちも、古来高貴の象徴とされてきた「紫」への思い入れが強かった。当時高価で貴重であった醤油を珍重していたのでむらさきと呼んだという説。
3. 醤油の原料の一つである大豆に、丹波の黒豆(むらさき色の大豆)を使用すると、醤油がむらさき色になったことから、「むらさき」と呼ぶようになったという説。
「さ=砂糖」「し=塩」「す=酢」「せ=醤油」「そ=味噌」のことで、和食における基本調味料。 この順番に味付けをすると料理がおいしく仕上がると言われます。それにはきちんとした根拠があり、 いちばん最初にあたる砂糖は浸透するのが遅いので早く入れて味をしみこませる必要があるとか。 また先に入れることで、他の調味料の浸透もよくする効果もあります。さらに塩は材料の水分を外に出す作用があり、 あまり早く入れると素材がかたくなってしまうそうです。醤油は早めに入れると、せっかくの香りが変わってしまうので、 料理が仕上がる前に加えるのが良いとされています。
日本中の醤油メーカーが2002年度に生産して出荷した醤油は約100万キロリットルになります。 これは、家庭で使われる量のほかに外食として使われる分、加工食品の原料として使われた醤油も含まれています。 この量は家庭で一般的に使用されている1リットルパックに置き換えると約10億本にもなります。 日本の総人口が約1億3千万人ですから、国民1人当たり、年間で約8本の醤油を使用していることになります。
1973年(昭和48年)、アメリカで醤油を製造したのが、日本企業の海外生産第一号。 その間の地道な販売活動と万能調味料「醤油」のよさが認められ、その後アメリカの全スーパーで扱われるようになりました。 現在では、ヨーロッパの主要なスーパーにも並ぶようになり、醤油は世界の多くの国々の家庭やレストランで親しまれています。
醤油は、うま味成分のアミノ酸、甘味成分のグルコース、酸味の有機酸、 香り成分のアルコールやエステル等々が渾然一体となってできた調味料。 ある実験によるとマイナス180℃でもシャーベット状にはなるものの、完全に凍ることはありません。
醤油業界では、醤油粕の再利用などにより、極力廃棄物を出さないようにとの考え方にたって、環境問題に取り組んでいます。 もともと、醤油の製造は主に植物原料を長い期間かけて醗酵醸造するという、環境保全を大事にすることにかなった製造方式が行われています。 企業の立地や企業規模により、取り組みの濃淡はありますが、環境保全についての自主行動計画の推進、容器包装のリサイクルなどについて、 業界揚げて推進するように努めています。
醤油をつくる後半の工程にもろみを絞る圧搾という作業があります。しぼった後に醤油の粕がでるわけです。 この「醤油粕」にも醤油同様に窒素分などの栄養素が含まれており、かつては「醤油粕」は全て畜産の飼料に利用されていました。 最近は畜産動物の用途ごとに配合飼料が低価格で供給されるようになってきたこと、また畜産農家が醤油工場よりも遠隔地にあることなどから、 全てを飼料に利用することが難しくなってきています。そのため、醤油業界においては、工場の熱源に利用したり、古紙に混ぜて紙として再利用、 バイオなどにより利用価値の高い飼料、肥料に利用するなどの取り組みをしています。


